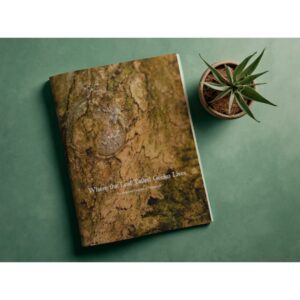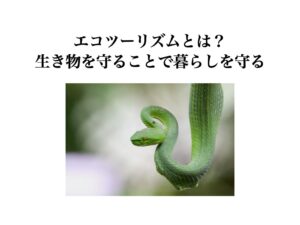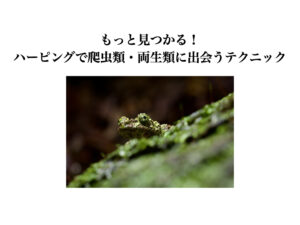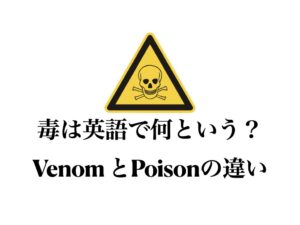ハーピングの意味
ハーピング(英語:Herping)とは、爬虫類や両生類を探して観察・撮影するアウトドア活動のことです。語源は「Herpetology(爬虫類両生類学)」に由来し、欧米を中心に広く使われている言葉です。
日本では「爬虫類・両生類観察会」といったイベントでも同じような活動が行われており、近年は一般の自然愛好家や写真愛好家にも人気が高まっています。
活動内容
ハーピングの基本は野外での観察ですが、内容は多岐にわたります。
- 昼間の森林や草原でのフィールド観察
- 夜間のナイトハイクで樹上性カエルやヤモリを探す
- 水辺での両生類の生態観察
- 施設や飼育個体の観察会に参加する
単に生き物を「見る」だけでなく、写真撮影、行動の記録、種の同定などを通して、自然との深いつながりを感じられるのが魅力です。

爬虫類・両生類を探しに行くのが好きな人はハーパーです
日本では、探しに行く人のことをハペ屋と呼ばれることもありますが、英語で言うとHerper:ハーパー(ハーピングする人の意)になり、爬虫類・両生類をまとめてHerps・ハープスと呼ぶことが多いです。
ハーピングの魅力と意義
ハーピングは単なる趣味にとどまりません。
- 多様な生き物との出会い:日本固有種や世界の珍しい種を実際に目にする体験はかけがえのないものです。
- 自然環境への理解:生息地の環境を知ることで、生態系や保全の重要性を実感できます。
- コミュニティの広がり:爬虫類・両生類観察会に参加することで、同じ関心を持つ仲間と交流できます。
ではなぜ、ハーピング(両生類・爬虫類)なのでしょうか。
世界に現存する爬虫類(約10,000種)・両生類(約8,000種)は殆どの種類で体が小さく、鳥のように長距離を飛行して移動することができません。総じて移動能力が高くないグループなのです。
その為、近年の急激な環境変化に適応できないグループは、移動して適するところに移住することができず絶滅の危機に瀕している種が非常に多くいます。
よく、このカエルは世界でこの湖にしか生息していません。という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。有名な、南米のチチカカ湖に生息しているチチカカミズガエル(Telmatobius culeus)もその一つで、世界でチチカカ湖にのみ生息します。

カエルを含む両生類は、卵に殻がないので繁殖場所が水場に限定され、更に皮膚には乾燥から体を守るための鱗がなく、生活を水のある場所に限定されるため、生息地を急速に広げることができません。もし、チチカカ湖の環境が急激に変わればこのカエルは環境に適応する間もなく絶滅してしまうのです。
そういった理由から、爬虫類・両生類は環境の変化を見るためにとても重要で、彼らのことを知ることが将来的には大きな環境変化のきっかけを知ることにも繋がります。
世界中で、爬虫類・両生類のことを気に掛ける人が増えて環境問題に意識を持ってもらう。その一つ目のステップがハーピングなのです。

注意点とマナー
観察や撮影の際には以下の点に注意が必要です。
- 野生動物への接触や過度なストレスを避ける
- 保護区や条例で定められたルールを守る
- 毒蛇や大型動物など危険を伴う生物に注意する
- 採集・持ち帰りは法律で規制されている場合があるため必ず確認する
まとめ
ハーピング(Herping)は、爬虫類や両生類を探して観察・撮影する奥深いアウトドア活動です。爬虫類・両生類観察会に参加したり、個人で自然の中に出かけたりすることで、思いがけない発見や出会いが待っています。
皆さんもぜひ、身近な自然から世界のフィールドまで、ハーピングの魅力を体験してみてください。